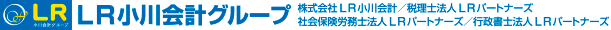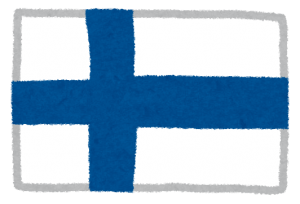過度の節税
4月19日最高裁判決

4月19日私たち税務関係者が注目する最高裁判決が出た。
90歳を超える男性がマンション2棟を金融機関から資金を借入して購入(相続開始前3年半前と2年半前)し、94歳で死亡、相続が始まった。マンションを購入しなかったならば課税価額6億円超となるべきところ、マンション購入により課税価額約2826万円、相続税「ゼロ円」になった。また、購入物件のうち1棟は相続税申告期限前、相続開始後8カ月後に売却されている。
この申告に対して課税当局は「本件購入・借り入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において相続税を減少させることを知り、期待して実行したものである。」として申告額を否認し、2億円超の追徴課税をしたのである。
最高裁判所はこの課税庁側の主張を認めて課税処分は確定した。
本件の節税スキーム
「タワマン節税」(ほっとタイムス2016年12月号)でも注目されたが、不動産と借入金による節税スキームは古くからある節税のスキームである。不動産の相続税評価が時価(地価公示価額)の80%程度に抑えられているため、不動産を購入すると、借入金で購入すると手持ち預金で購入するとにかかわらず、相続税の課税価額が不動産公示価額の概ね20%減額されている。
このような評価になっているのは相続は時期が不確定であること、相続税の納税のために処分しようとすると買いたたかれる可能性が高いこと、などを考慮して「課税の安定性を確保する」ため行政的に配慮されているものと理解している。
判決は妥当
しかし、今回の判例にあるように13億8千万円で購入したものが3億4千万円(購入価額に対して24・6%)で評価、申告(納税額「ゼロ」円)されていた。
このような極端な評価額の乖離は相続税法上「時価」とされている趣旨とかけ離れており何らかの措置が求められていたところでもある。
現在、相続財産の評価は相続税法上は「時価による」となっているが、税務行政の実務上は「相続税財産評価通達」によって評価しているのが実情である。しかし、評価通達制定当時と現在では超高層マンションの出現など評価の前提が大きく乖離してきているのも事実である。
最高裁判決はこの現実を、課税当局内の事務取扱に過ぎない評価通達の形式的な適用を排除したものとして私は高く評価する。
節税は納税者の権利
納税は憲法に定められた国民の義務ではあるが、租税の負担を軽減することは、「節税は納税者の権利」などと肩肘張って言わなくとも、納税者として当然のことである。
バブル華やかな頃、何度かアメリカ・ヨーロッパに視察に行ったが、自分の納税額を法に定められた範囲内で最小限にすることは、判例等の積み重ねの上で納税者の当然の権利として認められており、節税スキーム、節税商品が沢山紹介されて、私も納税者の立場に立った提案ができる税理士になろうと決意したのを記憶している。
節税の最もポピュラーな例を挙げると、個人事業主の「法人成り」という言葉がある。事業を個人で始めて、一定規模以上に規模が大きくなると「会社」にする、いわゆる「法人成り」である。
法人にすると、一般的には極めて節税効果が大きい。個人所得税の税率は国税である所得税、地方税である住民税と個人事業税の税率を合わせると最高限界税率は60%であるが、法人の税率は約39%であり、ある限度をこえると約21%の節税効果が生じる。このようにどのような法形式をとるかは個人の選択の自由である。
基準の明確化
通達は法律に非ず、と言われても通常用いられている評価通達に従って評価・申告した申告納税額が「ゼロ円」であったのに、3億円も納税しなさいと言われたら、納税者としては納得しがたい感情を抱くのは致し方のないことである。
財産評価基本通達第6項には「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官に指示を受けて評価する」となっている。
最高裁はこの規定に基づいた課税処分を容認したものであるが、この規定を適用する判断基準をはっきりと明示していない。
納税者を不安に陥れたり、ゆがんだ節税提案のブームを引き起こさないためにも明確な基準を示してほしいものである。
LR小川会計グループ
代表 小川 湧三

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします