消費税について考える①
消費税の逆進性議論
国会論戦が始まった。その中で身近な議論として消費税の逆進性議論がある。逆進性議論というと聞こえは良いが、「要するに低所得者は消費税を払いたくない」あるいは、「低所得者の生活を直撃する」から低所得者には消費税を負担させるな、
もしくは軽減させよという趣旨であろう。消費税の逆進性解消対策として議論されているのは、①複数税率制(軽減税率制)②給付付き税額控除制度があるが、今月はこれらの議論の問題点について、次号で消費税の持つ弱点の解消策について考えを述べてみたい。
税は誰にも不公平
税は収入・所得に掛かる所得課税、消費・支出に掛かる消費課税、財産に掛かる相続・贈与税に大きく分けられる。
上場株長者のように或るとき所得が突出している人、財産があってフローの所得はないが豪勢に暮らしている人(消費税の多額納税者)、使いきれず財産を残し相続税の納税に貢献している人、それぞれ人生のどのフェイズにいるかによって税のかかり方はさまざまである。
だから多額に納税する人は「なんで私がこんなに払わなければならないの」 と思っているのが実情ではなかろうか。「税はいつでも不公平・税は誰にも不公平」と思うのである。
これと同じように、今まで所得税を払っていなかった人々が消費税を払 うこととなると「なんで私が税金を払わなければならないの?」という感情を持ってもおかしくはない。
しかし、これは所得税の課税最低限を下げるのと効果はそんなに変わるものではない。消費税で考慮しなければならないのは、生活保護者や年金生活者など社会的弱者と言われる人々であろう。
一般に低所得者として括られる人々は、所得税制の中で考慮すればよいのであって逆進性云々は問題の本質をそらすものであり、極めて政治的なものである。
複数税率、軽減税率について
消費税は前段階控除方式というヨーロッパ特にフランスで始まったVAT(※)が中立的で簡素なシステムであるところから急速に普及したもので、膨大な取引を取引のつど中立・簡素に運営していくには複数税率にはなじまないものである。
この点は各種の調査報告書において実施各国の当事者へのインタビューなどでも明らかである。また、取引の脱漏を防ぐためにヨーロッパではインボイス方式を導入しているが、これはその国の納税者の質の程度を表すものであってVATの本質には関係なく、簡素な日本の方式が一番良い。
給付付き税額控除について
給付付き税額控除は複数税率、軽減税率制度よりもはるかに厄介な制度である。なぜなら所得税課税最低限以下の低所得者層の消費税負担を所得税の税額控除で対処しようとしているからである。
この低所得者の所得捕捉のためにマイナンバー制度を導入しようとするのは「牛刀をもって鶏を割 く」類のもので、この制度を導入しようというのは何か別の目的が隠されていると勘繰られても仕方があるまい。
給付付き税額控除には税制の根本的な問題も含まれている。一つは、現在個人課税になっている所得税制を「世帯課税」に切り替える必要があること。
二つ目は所得課税制度の中には非課税所得、所得控除、分離課税制度、源泉課税所得などが複雑に絡み合っており、可処分所得と課税所得の乖離があること。
三つ目は所得発生の頗行性(はこうせい)を考慮しなければ ならないこと。
四つ目は現在、所得税課税の対象から外れている膨大な人数の人たちを所得税事務の中に取り込むと実務の負担が膨大に膨れ上がることである。
給付付き税額控除で消費税の公平を論ずることは、実質的な可処分所得を考慮しなければならず、消費税という尻尾で所得税制、ひいては税体系の本体を振り回す結果となって所得税制全体をゆがめるものと考える。
(※) VAT=Value at Tax 《付加価値税》
税理士法人LRパートナーズ 代表社員 小川 湧三
神奈川県川崎市で税理士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


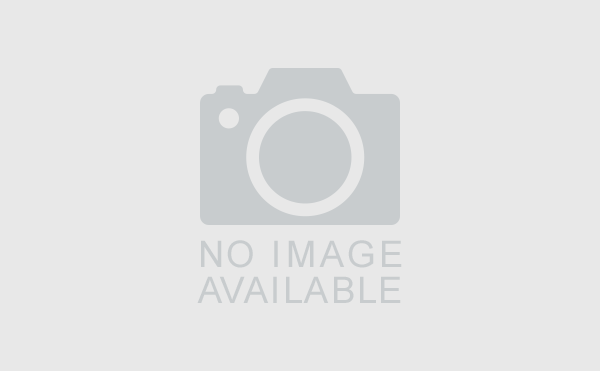
“消費税について考える①” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。