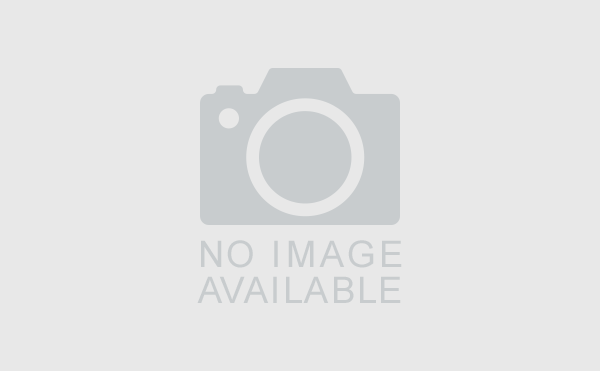方向違いの外形標準課税②
外形標準課税の導入
政府は来年から地方財政の減収を補う目的で都道府県民税を赤字企業にも課税するため所得以外の企業規模(B/Sでは資本金、P/Lでは付加価値)を基準に課税する外形標準課税を導入しようとしている。
外形標準課税は租税原則に反する
税金は個人であれば所得から生活費を差し引いた残額の中でしか負担できないし、企業であれば所得の中から企業を継続させるに必要な再投資資金を差し引いた中でしか税金を負担出来ないのは自明のことである。
外形標準課税の問題点は租税の担税力を所得ではなく企業規模に求めていることである。これは結果的には担税力のない赤字企業にも課税することになり租税原則に反するものと云わなければならない。
課税の根拠は、赤字法人でも経済的活動を行うにあたって公共財の便益を受けているから、と云われているが、既に同じ課税根拠として均等割課税が行われており、課税根拠としては薄弱であると。
外形標準課税はなぜ方向違いか
政府・日銀の経済政策における役割は失業とインフレをなくすことである。外形標準課税は人件費や支払利子、支払家賃などを含む付加価値を基準としているため、デフレから脱却しようとしている経済政策と相反することである。
すなわち、人件費について云えば既に賃金デフレの局面に入っていることである。さらに中国シフトにより国内の産業の空洞化が急速に進み5.4%と高水準に推移している失業率も更に増加することが予想されている。
このように人員整理を中心とするリストラが進んでいるなか、人件費への課税は企業のリストラを加速させるものである。また、支払家賃や減価償却費への課税は資本コストを増加させ投資への誘引を阻害し、投資促進を図ろうとする政府の方針の効果を減殺させるものである。
支払利子への課税は実質金利を増加させる。このような外形標準課税は、今でさえ倒産が増加し、廃業率が開業率を上回るという厳しい環境において、さらに中小企業の選別を強め企業の資金需要を衰えさせデフレを加速させるものである。
活力を民間へ、小さな政府を目指せ
いま、経済政策も税制も国民の活力を引き出すものでなければならない。税制は国民の生活や経済活動を阻害するものであってはならない(ドイツ課税違憲判決参照)。
第23号でも引用したように古代ローマの税制を調べた海野七生氏は「つまり、税金とは取りやすいところから取って済むものではなく、将来の生産につながる線上で考慮さるべきもの、と言うことである。」、また、「その税率で払われる税金で賄えない分野は民活にゆだねる。少なくとも2世紀までのローマ帝国は、現代の言葉を使えば「小さな政府」であったと確言できる。
21世紀は、どこの国で税金を払うかを、納税者が選べる時代になるだろう。税収を確保するためにも、税制度は「魅力的」に変わる必要がある。」と書いている。
現在のデフレを「小さな政府」への好機と捉え外形標準課税は導入すべきでないと考える。
(小川 湧三)
神奈川県川崎市で税理士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします