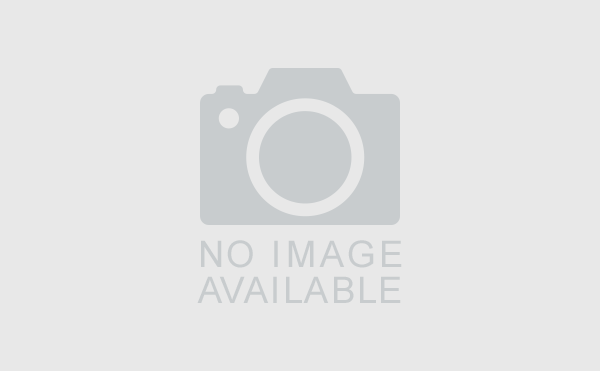街の「老舗」が潰される
街の「老舗」が潰される
このショッキングなタイトルは堺屋太一氏が文芸春秋2001年10月号に寄稿したタイトルです。
不良債権処理をめぐって金融機関が本来の業務の一つである「信用創造(貸し出し)機能」を失ったために、街の「老舗」に代表される間接金融に頼らざるを得ない中小企業は不良債権処理の過程において、かっての“貸し渋り“”貸し剥がし“のように支店長レベルでの競争意識のもとで犠牲になるのではないか、と危惧しているのです。同氏は次のように述べ、思い切った提案をしています。
『老舗がなくなるということは、単なる経済問題にとどまらず、商店街の衰退、コミュニティの崩壊につながります。「小さな商店や事業所がなくなり、大企業に集中するのは時代の流れ」という人がいますが、実は違います。アメリカでもヨーロッパでも新規創業が増加して、街が賑やかになっている。つまり、新しい発想での都市新生が必要なのです。
それが始まるまでの間、不良債権処理の猶予の線引きを、貸し手の金融機関の種類ではなく、借り手の債務金額の大きさにするべきです。さしあたり債務総額10億円未満の中小企業の不動産担保については、三年ないしは五年の猶予を設けてもよいでしょう。そして、その間に、新しく活力ある自営業を育てる新規創業を活発にするのです。』
中小企業をもっと大切に扱ってほしい
竹中財政相は不良債権問題に関していえば、大手30社の不良債権が解決すれば、不良債権処理が完了するかのごとく発言していますが、上記堺屋氏が述べているようにその下流には膨大な中小企業があるのです。
上場大企業の雇用数は500万人台で就業労働者5000万人の10%程度です。中小企業は雇用の90%を担っていることになるのです。その中小企業経営者は失業保険をもらうどころか、身銭を切って頑張っています。その中小企業が今が音を挙げ始めている。
セーフティネットは創業をしやすくすることも大事ですが、既存の中小企業がもっと希望をもてるようにするところから始まるのではないでしょうか。
中小企業の生き残る道
金融システムが機能しなくなってしまった現在、20%以上が債務超過の状態にあるといわれる中小企業が生き残る道は非常に厳しいものがあります。債務超過状態であっても実質は経営者が過去の蓄積からの吐き出しによるものが大半です。
しかし、経営者の蓄積も限界に近づいてきています。堺屋氏が提案しているように「さしあたり債務総額10億円未満の中小企業の不動産担保については、三年ないしは五年の猶予を設けてもよいでしょう。」という提案でも3-5年に業績が回復するという見込みが立たない状態ではさして効果が出ないでしょう。
思い切って20-30年のリスケジューリングを政府施策で実施するくらいでないと中小企業は安心して経営改革に動けないと感じています。
今まで政府の施策を信じながら「ゆで蛙」状態に陥っている中小企業は動くに動けない状態にあります。金融機関からの融資も期待できなくなった中小企業は、「地域通貨」システムなどの新しい試みも始まっていますが、昔の「頼母子講」や「無尽」などの制度を復活させて相互金融の自衛手段を具体的に取り上げなければならないかもしれません。
(小川 湧三)
神奈川県川崎市で税理士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします