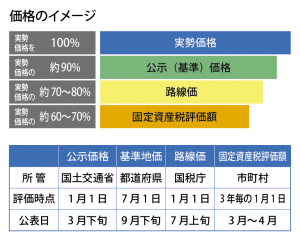電子取引データの保存についてご確認ください

改正電子帳簿保存法が今年の1月1日より施行されました。準備のために電子取引について今一度確認してみましょう。令和4年1月1日以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、そのオリジナルの電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です(義務化まで2年の猶予期間が設けられ2年間は引き続き紙での保存も容認されます。令和3年12月6日付『日本経済新聞』朝刊より)。
❖電子データの保存の要件は?
①改ざん防止のための措置をとる
システム導入などの費用をかけない方法として、「改ざん防止のための事務処理規程」のサンプルが国税庁のホームページで公表されています。
②日付・金額・取引先で検索できる
検索機能を確保する簡易な方法として、◎電子データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておく方法◎表計算ソフト等で索引簿を作成しておく方法などがあります。
③ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
❖電子データの保存方法は?
①電子メールに請求書等が添付された場合
・電子メール自体をサーバ等に保存する(メール内容をPDF等にエクスポートしての保存も認められます)
・添付された請求書等をサーバ等に保存する
②発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする場合
・ウェブサイトに領収書等を保存する
・ウェブサイトから領収書等をダウンロードしてサーバ等に保存する
・HTMLデータで表示される場合は、ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバ等に保存する
③第三者等が管理するクラウドサービスを利用し領収書等を授受する場合
・クラウドサービスに領収書等を保存する
・クラウドサービスから領収書等をダウンロードして、サーバ等に保存する
④従業員がスマートフォン等のアプリを利用して、経費を立て替えた場合
・従業員のスマートフォン等に表示される領収書データを電子メールにより送信させて、自社システムに保存する(この場合、スクリーンショットによる領収書の画像データでも可)
ご不明な点は弊社担当者までお問い合わせください。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします