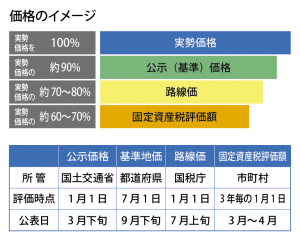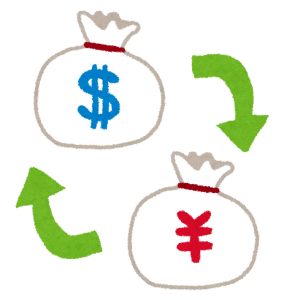贈与税の歴史

贈与税は、令和3年度の税制改正大綱の中で、諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税の一体課税の観点から見直しの議論を本格化させるとの文言が謳われ、今後、改正が見込まれています。
今回はこの贈与税の主な歴史を見てみましょう。
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
♣贈与税はいつから
贈与税は、1947年(昭和22年)から生前贈与による相続税回避の防止を目的として贈与税が創設されました。
♣贈与税の課税方式
贈与税の課税には、贈与者に課税する「贈与者課税」と受贈者に課税する「受贈者課税」の2つがあります。日本では当初の2年間は贈与者課税を採用しておりましたが、その後現行の受贈者課税に変更されました。
日本と同様に受贈者課税を行っている国は、ドイツ、フランスで、贈与者課税を行っている国は、アメリカ、イギリスです。
♣基礎控除の変遷
昭和28年から昭和32年10万円
昭和33年から昭和38年20万円
昭和39年から昭和49年40万円
昭和50年から平成12年60万円
平成13年から現在まで110万円
♣相続時精算課税制度の創設
平成15年より相続時精算課税制度が創設されました。相続時精算課税制度とは、贈与時には2,500万円までは無税で、それを超える部分は一律20%の贈与税が課税され、相続時に、その贈与された財産を相続財産として繰入をして精算するというものです。
これは、贈与者毎に通常の贈与(暦年課税)と相続時精算課税と選択ができ、相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税の適用ができなくなるというものです。
♣今後の方向性
現在は、相続があった場合に通常の贈与の相続財産への繰入期間が、相続から3年以内になっており、3年を超えるものは、相続税の対象から外れています。
今後の議論としては、この期間をもっと長くする、若しくは相続時精算課税への一本化などの議論が予想されています。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします