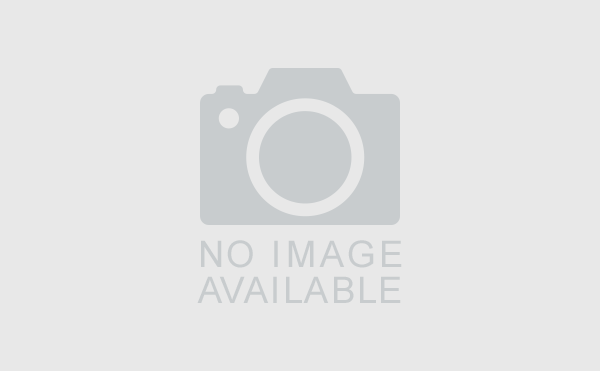災害時の組織体制“マニュアル化のすすめ”
熊本地震では、大変痛ましいことに多くの犠牲がありました。経済面でも、多くの事業所が閉鎖、操業停止となり、いまだ、その影響を残していると思います。一日も早い復興をお祈り申し上げます。
災害は忘れた頃にやってくるといいますが、大きな災害を目の当たりにし防災意識の高まっている今こそ非常時の体制について考える時です。
会社としては、防災マニュアルを定め、救助・避難・備蓄など様々な項目を定めておく必要があります。ここでは被災直後の労務判断と本部機能について説明します。
災害時の労務管理については、防災マニュアルに定めておき、必要な際には、すぐ閲覧できるようにしておきます。防災訓練時にも内容を確認します。いざという時は、焦りますので日頃の準備、練習が必要です。
被災の時刻・規模によりますが、操業ができるのかどうか、復旧作業にとりかかれるか、または避難するべきか、などの判断をする必要がありますし、次の作業などを行うための人員が本部機能として必要になってきます(応急救護指示・被災程度の調査・従業員と家族の安否確認・保安、防犯体制の確立)。
速やかに対応できるよう構成メンバーと設置基準、設置場所と、役割分担を決めておく必要があります。
就業時間外に、被災した場合に備えて、各自の判断で集まれるように集合の条件と集合場所を決めておきます。会社が被災して近づくことができない場合に備えて、第2候補地も決めておく必要があります。
構成メンバーは、交通手段が途切れる場合も想定して徒歩や自転車で通勤可能な人や社の方針を決めることができる責任者も加えておくことが必要です。また、権限代行順位なども決めておきます。本部機能は、意思決定・連絡機関であり、その後必要に応じて従業員を動員します。
これらのことを、決めておくだけでも混乱を減らすことができ、必要な対応を素早く行うことができます。防災の設備とともにマニュアルの整備をおすすめいたします。
またもう少し範囲を広げて「事業継続計画(BusinessContinuityPlan)」を意識してみることもよいでしょう。
このBCPに関しましては、「東京商工会議所版BCP策定ガイド」が参考になります。
http://www.tokyo-cci.or.jp/survey/bcp/
このガイドのとおり全てを一度に整えることは難しいですが、東日本大震災の教訓から整備されていますのでこの機会に一度ご覧ください。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします