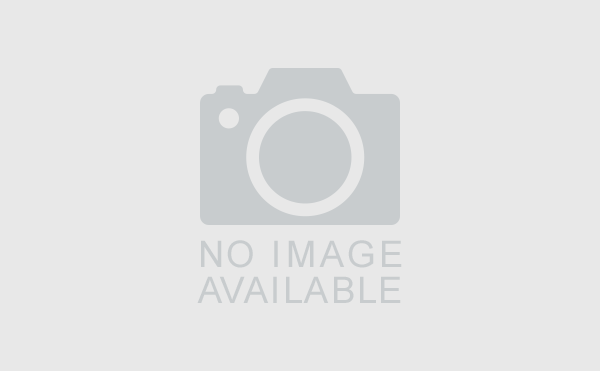「所得格差」
古いはなし
20数年前、1989年ベルリンの壁に穴が開き共産圏が崩壊したとき、これからどうなるのかといろいろ考えていたが、特に私が予想していたような変化はすぐには起きなかった。
しかし、その当時感じていたことが間違っていたのではなく、緩やかに進行していてそれが顕著になったのはこの十年ではないかと思っている。時間の観念が入っていなかったために 現実社会にはすぐ反映されなかったのだと思えるようになった。
沈む時は下から濡れる
一億総中流時代といわれた1980年代からバブル崩壊を経てデフレに突入した1997年以後に派遣村が話題になった頃から格差が言われるようになったと思う。いま生じている所得格差の発生の根源を遡(さかのぼ)れば、共産主義の崩壊に行き着く。
自由主義と共産主義というイデオロギーの壁が崩壊して、世界からイデオロギーによる大きな対立がなくなった。しかし、すべての対立が解消したわけではなく、一つの制約条件が解消すれば、また、新たな制約条件が出てくるが、ともかく世界のグローバル化が始まった。
しかし、制度、技術、資本等の目に見えないソフト・システムの壁が厚くイデオロギーの壁崩壊の影響はすぐには現れなかった。開発途上国がテイクオフしたのはソフト・システムの壁が解消し始めた2000年に入ってからの事であった。水は高きより低きに流れるように、先進国から旧共産主義国、開発途上国へどっと流れ始めた。
70年代アメリカの平均賃金が日本やドイツの追い上げによりなだらかに右肩下がりを続けたように、今度は先進国全体が同じ立場に立つのである。
所得格差はなぜ生じるか
全体右肩下がりになれば、所得格差が拡大するのは当然である。経済に歪みが生ずれば被害を受けるのは上流層よりも下流層である。その歪みにより直ちに影響を受けるのは所得の低い人、日々の生活を労働所得に頼る人たちである。
グローバルシフトにより長期下降期に入った旧自由主義諸国は「1% vs99 %」に象徴されるように金融の歪み(バブル)が爆発する都度下流層はさらに下流へ、上流層はストローで吸い上げられるようにさらに上流へと集約されていく。
この 20 年間所得の動態的二極分化は自由主義・資本主義諸国に構造的に組み込まれてしまっているのである。堤未果氏のドキュメンタリーは見事このことを突いている。
所得格差が生じる原因にはもう一つ、いわゆる世代間格差に象徴される長寿社会の到来がある。成長期に働き、それなりの所得を形成した人たちと下降期に入って就業した若い人たちとでは所得形成に格段の差が生じていて、このままでいけば先進国の格差拡大はさらに進行していく。
格差解消に向けて
民主党は所得格差の現象面に目を奪われて、弱者対策と称して金銭補償を中心とした対策を打ち出しているが、これは格差を解消するどころか逆に格差を拡大してしまうのではなかろうか。
細かく論じることは避けるが、産業政策を成長期の産業政策から下降期の産業政策へ転換しなければならない。「競争による奪い合い」から減少する「パイを分かち合う」産業政策へ政策の在り方を変える必要がある。
特に中小企業政策は先端技術や先端産業政策とは異なり協調を生み出す政策が必要である。お金がお金を生み出す金融資本主義から、労働がお金を生み出す産業政策へ切り替えないと強者はますます強く、弱者はさらに弱く消えざるを得ない社会になってしまう。
昨年アメリカ・ニューヨークで起きた「1% vs99 %」デモや、いま、ヨーロッパで吹き荒れている失業の嵐のように、これから日本で吹き荒れるであろう失業の嵐も避けられず、所得格差の拡大はさらに続くであろう。
税理士法人LRパートナーズ 代表社員 小川 湧三
神奈川県川崎市で税理士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします