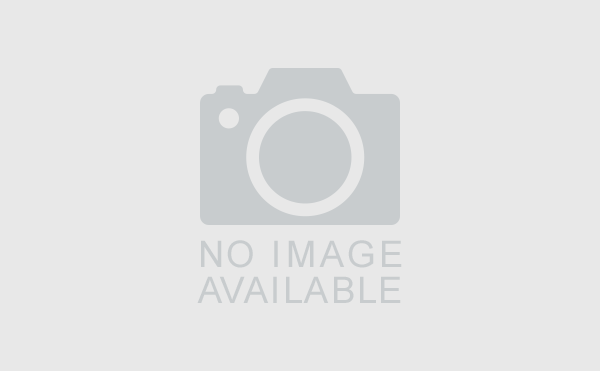海外進出の新しい視点
アジアは日本のマーケット
身近になってきた中小企業の海外進出
私の身の周りにも東南アジアへの進出の話を聞くことが多くなってきた。身の周りでは、いま、ベトナム、カンボジアへの進出が大きなトレンドとなりつつある。昭和 52・53 年頃にはじまった中小企業の海外進出は、何度かのブームを経て現在に至っている。
私が中小企業の海外進出に関心を持ったのは、中国の郷鎮企業を見学してみたいと思い「改革開放」政策が始まって間もない1992年に深圳(シンセン)へ行って以来である。1994〜5年にかけては大田区を中心とする京浜工業地帯の中小企業 20 数社のベトナムのタントワン工業団地への進出にもかかわった。
インド・ムンバイの中小企業の視察は1998年に行ってきた。しかし、当時の企業は日本との合弁企業が中心であって、現地の中小企業には見るべきものがなかったように思う。
アジアは日本と同じ道 を歩き始めた
昨年末、ある海外進出セミナーに参加した。注目すべき点はいくつかあったが、特に『目からうろこ』であったのが、日本は東南アジア諸国がこれから歩く未来像であるということである。
ミャンマーが昨年軍事政権から緩やかに民政へ移行したことで、東南アジア全域が日本が明治以後歩いてきた道、終戦後歩いてきたと同じような発展過程を歩きはじめた。それは工業化、産業化による大量の工場労働者群や中間所得層が生まれはじめていることである。
私が中小企業の視察をはじめた1990年代の東南アジアは、戦前の日本の状態、もしくは終戦直後から昭和 20 年代の感じであった。インドでは中小企業の社長が1年後にできる新工場の完成予想図を前にして大きな希望を語っていたことを思い出す。
日本はアジアの未来
日本の戦後の発展は朝鮮戦争の勃発とともにはじまった。私が中学生の時である。軍需景気とともに日本産業は発展期に入り、猫の手も借りたいくらいの時代、「金の卵」 の集団就職、就職列車が上野駅を賑わした。
やがて集団就職で「金の卵」 を集めてきた時代が終焉 し、昭和 30 年代から 40 年代にかけて、「三種の神器」 をめがけて旺盛な需要が沸き起こってきた。
工業化により大量の労働者層を中心とする中間層が生まれてくる東南アジアは資本主義工業化社会であり、戦後の日本社会と同質なものであると考えられる。日本と同質のマーケットが東南アジアに35 億人の人口を持って出現し、あるいは出現しつつあるのである。
アジアは日本のマーケット
東南アジア諸国の現状を見ると中国は集団就職の時期を終えた時期に相当するように思えるし、ベトナムはいま集団就職の時代がはじまったように思って差し支えない。
このような新しいマーケットに合わせるには、「タイムスリップ」してみることが一番である。単に当時のものをそのまま持ち込むのではなく、現在の最新の技術・手法を使いながら、過剰な技術・手法をそぎ落とし、真に必要なところ、マーケットにマッチしたところに絞り込んで商品やサービスを提供していく必要がある。
9日のテレビでは昭和 40 年代に流行った 「巨人の星」を野球文化のないインドで野球をクリケットに置き換えて売り出す企画が放映されていた。先の海外進出セミナーでは、このマーケットに適合させる経営手法を「スマート・リーン経営」として紹介していた。
こうしてみると、今までの海外進出は製造業が中心であったが、これからは商業やサービス業へ広がり下請け製造・加工業ばかりではなく物販、飲食その他の中小企業、さらには農業、観光業や沢山のサービス業にも海外進出できる土壌ができつつあり、チャンスが回ってきたのである。
(税理士法人LRパートナーズ 代表社員 小川 湧三)
神奈川県川崎市で税理士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします