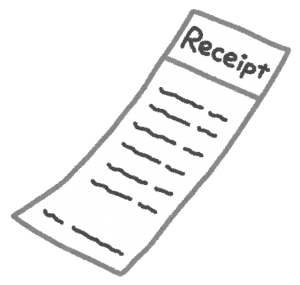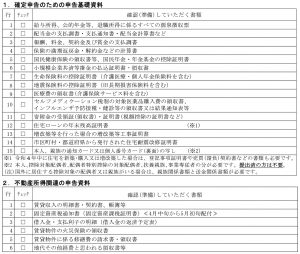どうする電帳法(電子帳簿保存法)
◆電子取引の保存時期
令和6年(西暦2024年)電子取引の保存義務化への対応が求められます。
※税制改正等に変更や特例の記載がある場合を除く。
◆電子取引を大雑把に理解する
紙を除く取引証明の授受を指します「メールの添付ファイル、インターネットで表示される領収書、利用明細等と多岐に渡る」。
◆予算に応じた選択肢
予算不要
⒈国税庁HPの「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定」をひな形とし、事務処理規定の作成と遵守。
⒉ファイル名もしくは管理台帳に「取引日付、金額、取引先」を記録し、検索可能な状態とする。
予算あり(予算の範囲で機能追加や代行)
JIIMA認証製品を導入の上、販売元の指示に従ってください。認証製品は国税庁の「JIIMA認証情報リスト」のページより確認できます。
注意事項
一般的に普及しているもの、ハードルが高い項目は記載を省略します。IT導入補助金、持続化補助金などもご検討ください。システム利用料、保管サービスなどは継続して発生することがあります。
◆電子取引以外の対応(義務化対象外)
電子帳簿・電子書類の保存
自己の作成する帳簿書類が対象。会計ソフト等の電子データがそのまま利用できる。社内の「国税関係帳簿に係る(中略)事務手続きを明らかにした書類」が必要となる。
紙の取引書類の保存(スキャナ保存法)
紙で受渡される書類(契約書、請求書、領収書)などが対象。スマホやデジカメ、スキャナーなどを利用して電子データ化したものを利用可能。
撮影データや記録事項、管理体制など要件も多いため、システム導入推奨。
◆終わりに
法改正によって対応が必要となるのは電子取引だけですが、後述のいずれかに魅力を感じるなら検討の価値があるかもしれません。紙管理廃止、働き方改革、青色申告控除や拠点間連携、不正対策、データ活用などの付属サービスなど。対応にあたっては最新の情報を確認することを推奨します。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします