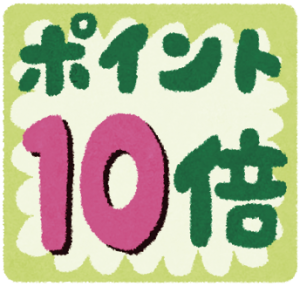貸借対照表で安全性分析

貸借対照表は会社のある一定時点での資産・負債・純資産の残高を記載した書類で、財政状態を表す資料です。資産と負債は短期と長期で区分をし、短期的なものを流動資産、流動負債、長期的なものを固定資産、固定負債とします。純資産は資産から負債を控除したもので、資本金や今までの利益の合計額を示しており、返済義務のない資産です。
貸借対照表から安全性を分析するためには、資産や負債の流動と固定を正確に区分することが大切です。流動資産は短期間に現金化できる資産で、現預金、売掛債権、棚卸資産、その他一年以内に回収できる貸付金等などです。流動資産の中に長期間未回収となっている売掛金や貸付金が入っている場合は流動資産から投資その他の資産へ区分を変更しましょう。流動負債は一年以内に支払う予定のお金のことで、買掛金や未払金、一年以内に返済の借入金、預り金などです。長期借入金やリースの金額も一年以内に支払う金額を流動負債に区分しておきます。
♣流動比率、当座比率
短期的な安全性を流動比率、当座比率で確認してみましょう。これらは会社の一年以内の支払い能力がどの程度であるかを表します。
流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100
流動比率が100%以上であれば、一年以内に入ってくる現金で支払いを賄えるということで、流動比率が高いほど短期的な安全性は高いといえます。一般的に120%ぐらいの数値であれば安全性が高いといわれています。棚卸資産に不良在庫が含まれている場合は除外して計算しましょう。
当座比率(%)=当座資産÷流動負債×100
流動資産から棚卸資産を除いたものを当座資産といい、より現金化しやすい資産だけで流動負債をどれだけ賄えるか、短期の安全性をシビアに判断できるのが当座比率です。
♣自己資本比率
長期的な安全性を確認する指標の一つに自己資本比率があります。
自己資本比率(%)=純資産÷総資本×100
総資本は負債と純資産の合計のことで、自己資本比率が高いということは、調達した資金のうち返済不要な資金の割合が高いということなので、財務面の安全性が高いといえます。一般的には40%以上であれば、安全性に問題はなく銀行や取引業者からの信用度が高いです。
貸借対照表に注目して、残高や区分が正確かをあらためて確認し、安全性を分析してみましょう。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします