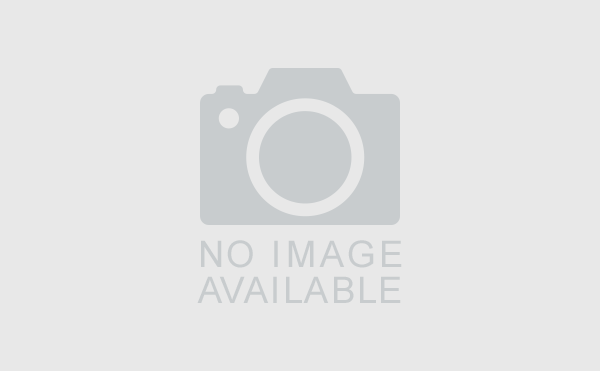職場で活かすプライミング効果
1 記憶の刺激の仕組み
心理学にプライミング効果と呼ばれるものがあります。これは、あらかじめ受けた刺激(例えば言葉や行動)が、その後の連想に作用し、人の言葉や行動にまで影響を与えることをいいます。
例えば森と聞いて連想するのは青や赤よりも緑です。当たり前ですが、脳の中でそれぞれのイメージが紐付けられているので、関連のより強い方として緑を連想するわけです。
では、例えばリンゴという言葉を聞いたとき、丸い、赤い、甘酸っぱいなどのリンゴの持っている属性がまとめて刺激され活性化します。これらは脳の中で同じリンゴという言葉に結びついているからです。先にリンゴのイメージによって記憶が刺激されているときは、赤いや丸いといったイメージが活性化しています。
ここでまったく無関係な「野球に使う道具といえば?」と言う質問をしたとします。すると質問に対しバットやグラブと答える確率よりも形が丸いボールと答える確率が高くなりますし、刺身といえば?と聞かれたら白身よりも赤身の例えばまぐろと答える確率よりも多くなります。
この効果はまったくの無意識でおこります。自分では、刺激である特定のイメージが活性化していることを自覚できないのです。
2 言葉の影響
つまり、受けた刺激によって知らずに先入観を持った言動をしてしまうということです。その影響は決して軽くありません。海峡を進む連絡船のように人の意識は情報の荒波に揺さぶられています。連想が連想を生むなら、最初の刺激(言葉)はとても重要だということになります。
3 職場での応用
どうやら、よい組織風土を維持するには普段の言動が重要と言えそうです。疑心や無気力、利己主義等のイメージが活性化された脳が集まる職場環境は普通に考えてよくありません。また、自分が発した言葉によって一番影響を受けるのは自分自身だと言われています。気持ちよく仕事するためにも、自らの言葉使いを振り返ってみる必要があるようです。
注意喚起やミスのチェック等にも応用できますので、ぜひ職場でこのプライミング効果を意識してみてはいかがでしょうか。
では、最後に質問です。雪降る地方の県をひとつ思い浮かべて下さい。
この文章を読み直して回答と関連のあるキーワードがみつかればそれはプライミングの影響かもしれません。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします