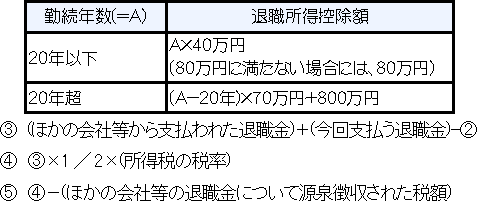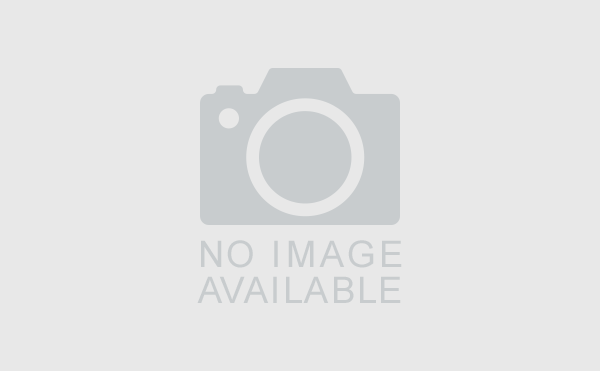同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの所得税の求め方
一昨年あたりから、団塊の世代の方が定年退職されると云う事を耳にしますが、そこで退職金の所得税について
同じ年に2か所以上から退職金をもらった場合
はどう計算するのでしょうか?
役員又は使用人に退職金を支払うとき、同じ年にすでにほかの会社などから退職金をもらっていることがあります。また、1つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもあります。
これらの場合には、ほかの会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければなりません。
まず、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」とすでにほかの会社等から交付されている「退職所得の源泉徴収票」の提出を受けてください。「退職所得の受給に関する申告書」には、以前に受けた退職金の金額、源泉徴収された税額、支払年月日、勤続年数などを記入してもらってください。
次に、源泉徴収する所得税額の計算を、これから説明する順序で行ってください。
①勤続年数を計算します。
ほかの会社などから支払われた退職金と今回支払う退職金のそれぞれの勤続期間のうち、一番古い就職の日から今回の退職の日までの期間が勤続年数となります。勤続年数に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。
A社(98年4月入社)を07年3月、B社(01年4月入社)を07年7月に退職した場合 B社で源泉徴収するときの勤続年数は、一番古い就職の日(98年4月)から今回の退職の日(07年7月)までの9年4か月になりますので、端数を切り上げて10年になります。
② ①で計算した勤続年数に応じて、上の表により退職所得控除額を計算します。
この差引きをした後の金額が、今回源泉徴収する所得税額です。
差引きの結果、源泉徴収する所得税額がマイナスになったときは、源泉徴収をしないで退職金をそのまま支払ってください。
この場合、マイナスの金額の還付を受けるためには、役員又は使用人が確定申告をする必要があります。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合には、退職金の支払額から、一律に20%の所得税を源泉徴収しなければなりません。
この源泉所得税は、役員又は使用人が確定申告で精算することになります。
(出典 国税庁ホームページ タックスアンサー 2735)
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします