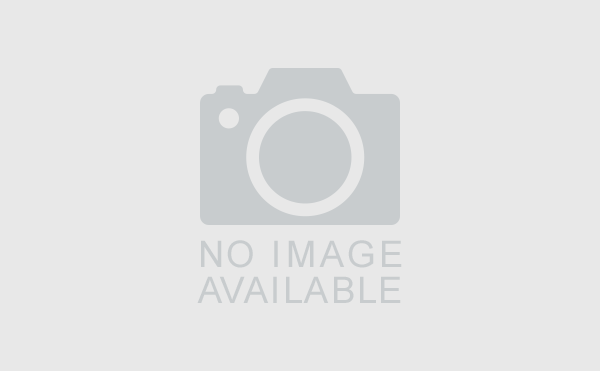会社が行うべきハラスメント対策について

近年は、産業構造や働き方の変動により、以前は問題とならなかった、あるいは文化として黙認されていた事案がハラスメント扱いされるようになりました。
終身雇用制度が保障されており、上司に従っていれば出世も約束され、定年まで給与が右肩上がりという時代であれば、我慢をすれば見返りがありました。しかし、終身雇用制度が崩壊し、出世や右肩上がりの賃金が約束されていない現代の若者に我慢を強いるのは、見返りがない分無理があります。
したがって、以前にも増して会社のハラスメント対策構築が急務となりました。
そこで、ポイントを絞って会社が講ずべき事項並びに対応策についてご紹介いたします。
会社が準備しておくもの(主なもの)
会社がハラスメントに対してどのような姿勢で臨むかが問われます。
① 就業規則等に規程を設ける
◉どのようなことがハラスメントに該当するのか、そしてハラスメントを行った場合の懲罰について周知します。
② 相談窓口の設置
◉小規模事業所等で窓口を設けるのが難しい場合には、弁護士や社会保険労務士等、外部に委託することも可能です。
③ 研修
◉ハラスメントの典型例や対応策を学ぶだけでなく、心構えも学びます。
※厚生労働省のホームページ等で研修の題材を得ることができます。
対応策
ハラスメントに該当するか否か(結論)とその理由を明確にし、処分を決定するようにします。
この際に特に留意すべき点は、ハラスメントの程度に比べて過大な懲罰を課したり、同じ内容のハラスメントに対して人によって懲罰の程度や内容が異なることのないようにすることです。
明らかに過去の例からハラスメントとわかる事案については説明するまでも無いですが、問題は責任の所在が不明確であったり、ハラスメントと言えるか微妙なもの(グレーゾーン)に該当する事案です。
例①
育児や介護で休業する社員がいる部署において、人を補充せずに仕事をその他の人に振り分け、残業代の支給はおろか、何の見返りもなかった為、休んでいる人に不満の矛先が向かってしまったケース
結論:
ハラスメントに該当するが、当該加害者に対しては厳重注意に留め、是正を求める。
合わせて会社も是正を求める。
理由:
過去の判例等によって、ハラスメント案件ではあるが、会社にも帰責事由がある。
例②
皆が許されている呼称について、ある人だけがセクハラだと訴えられたケース
結論:
ハラスメントに該当しないが、是正を求める(もちろんその他の人に対しても)。
理由:
平等の原則に反するため。

例③
何度注意しても行動を改めない社員を強く叱責したケース
結論:
ハラスメントにも該当せず、是正も求めない。
※もちろん、大勢の前で吊るし上げる等の行為は論外です。
理由:
強く叱責することで本人の自覚を促す必要があったため。
〈まとめ〉
ハラスメントに対し、必要以上に萎縮してしまうというご意見も聞きます。
しかし、会社として真摯にハラスメント対策に取り組み、従業員相互が相手を尊重する姿勢でいれば、自ずと重大な事案は防げます。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします