高額療養費制度
高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払戻される制度です。
■ 対象となるのは、健康保険が適用になる診療にかかった費用のみです。従って、先進医療にかかる費用、入院時の差額ベッド代、食事代等は対象外です。
■ 自己負担限度額は、年齢および所得により異なります。
70歳未満の方は所得に応じ以下の5区分で、それぞれ自己負担限度額の計算式が定められており、区分オで約3万5千円です。
・区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)
・区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)
・区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)
・区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
・区分オ(住民税非課税世帯等)
70歳以上の方は、所得に応じて、「現役並み所得者」「一般」「低所得者(住民税非課税等)」に分かれ、それぞれ自己負担限度額が設定されており「一般」の方で1万8千円です。
■ 同一世帯(被保険者と扶養に入っている人)で複数の人が医療費を支払った場合や、一人が複数の医療機関を受診した場合、または入院と外来で受診した場合など、自己負担額(それぞれ2万1千円以上のものが対象)を世帯で合算することができます。(世帯合算)
■ また、高額療養費として払い戻しを受けた月が直近12カ月間で3回以上あった場合、4回目以降は「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに引き下げられます。
高額療養費の申請方法は主に以下の2つがあります。
■ 一つは事後申請で、医療機関の窓口で一度医療費の自己負担分を全額支払い、後日、協会けんぽ等、加入している公的医療保険に申請して払い戻しを受けます。申請期限は、医療機関で支払いをした日の翌月初日から2年間です。
■ もう一つは「限度額適用認定証」を利用する方法です。事前に加入している公的医療保険に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けます。医療機関の窓口でこの認定証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用している方や、70歳以上の方(一部を除く)は、限度額適用認定証がなくても窓口での支払いが自己負担上限額までとなる場合があります。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします



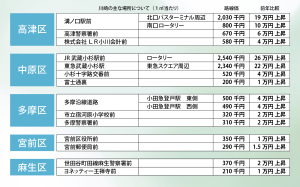
“高額療養費制度” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。