システム障害
ETCトラブル
 4月初め東名高速道路や中央自動車道など17路線の106カ所でETCが利用できなくなるシステムトラブルが発生した。
4月初め東名高速道路や中央自動車道など17路線の106カ所でETCが利用できなくなるシステムトラブルが発生した。
ETCは1日770万台、高速道路を利用する車両の95・3%が利用する不可欠のインフラである。
ETCの目的は料金所をそのまま流れを止めないことであるが、ETCが原因で大動脈が滞ったのである。
原因は新しい割引システムを入れるところで発生した。継ぎはぎ改修の限界で物流を止めずに改修することの難しさを露呈したのである。
金融機関のシステム障害
金融庁は昨年6月「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」を発表している。
2013年10月10日~11日に安定した稼働実績を誇っていた全銀システムが大規模な障害を起こした。
2日間にわたって一部の銀行の振込業務が麻痺したために500万件以上の振り込みに影響が生じた。
これまでコストは高くても「安心・安全」を売り物にしてきた全銀システムの今後に不安を抱かせるトラブルであった。
また、金融機関のシステム障害と言えばみずほ銀行のシステム障害がよく知られている。みずほ銀行は第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行のリテールバンキングを継承する旧みずほ銀行とホールセールバンキング事業を継承する旧みずほコーポレート銀行がそのシステムの統合に失敗したために生じた。障害の詳細は省くが、2002年4月から2022年10月まで7回に及ぶシステム障害を起こし預金者やATM利用者に大混乱が生じた。
① 2002年4月:ATM
② 2011年3月:東日本大震災義援金振り込みによる上限超過
③ 2015年1月:ネットバンキング
④ 2021年2月~3月(4回)
⑤ 2021年8月~9月(3回)
⑥ 2021年12月~翌年2月(3回)
⑦ 2022年10月:ネットバンキング
日本の企業の多くは既存の基幹システムに改修を重ねてきた。このため内部構造が複雑になり全貌を知る人材にも乏しく、中身も「ブラックボックス」になりがちだ。
ETCシステムやみずほの金融システムのように継ぎはぎが多いと改修時に障害が発生しやすくなる。
ETCや金融システムのような公共性の高いインフラを支えるシステムは常時稼働が求められており、稼働させながらの大規模な改修はさらに難しい。
システムの脆弱性と犯罪
システムの脆弱性に付け込んだ犯罪も多発している。
ETC障害のように意図しないで起きる障害もあるが、深刻なのは意図的にシステムが外部から攻撃される場合である。身代金目当ての「ランサムウエア」のようなもの、密かに侵入しデータの窃盗や破壊を行うもの、AIの発達により真偽不明の情報操作や、アメリカの大統領選挙で噂されたような情報操作も行われていると聞く。
意図的な小さなシステム障害
私がシステム障害に関心を持ったのは2015年春にたまたまミャンマーへ行く飛行機の中で機内のドラマを見ているときに相棒シリーズの「X-DAY」を見てからである。
ある金融機関のシステム障害を機に取り付け騒ぎが起き、回り回って「X-DAY」が起きた。しかも、よく調べてみるとシステム障害は人為的に引き起こされたものだった。つまり「X-DAY」は意図的に引き起こされたものであった。というストーリーだったと記憶している。
その後、システム障害に関する小さな記事をウォッチしていると
① 2015年5月21日:東日本信金システム
② 2015年9月8日:住信SBIネット銀行
③ 2018年5月14日:ゆうちょ銀システム障害
④ 2016年9月29日:横浜銀行など4行
など小さなベタ記事で報道されているのを見つけた。
2年で4回、5月と9月、計ったようにシステム障害が起きていてドラマの先見性、信憑性に驚いた記憶がある。
前述したように犯罪や大きな障害が多発している現在、このような小さなシステム障害が意図的に起こされる危険が危惧されるのである。
時あたかもトランプ・リスクが懸念されている現在、トランプ・リスクに便乗したシステムトラブルを引き起こしかねない。
ちょっとした出来事が「X-DAY」の引き金を引くことのないように願うのみである。
LR小川会計グループ
代表 小川 湧三

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします


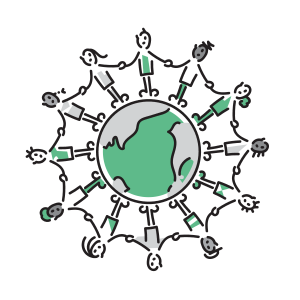

“システム障害” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。