税の国際協調①
 先月に続き国際協調についてです。税の世界でも多くの国際協調が行われてきましたが、簡単に実現したわけではなく、長い時間をかけて議論が積み重ねられてきました。
先月に続き国際協調についてです。税の世界でも多くの国際協調が行われてきましたが、簡単に実現したわけではなく、長い時間をかけて議論が積み重ねられてきました。
まずは課税権の問題です。原則、本店所在地や居住地国に課税権がありますが、グローバルな経済活動については、消費地(使用)国や付加価値をつけた国も税収確保のため課税権を確保したいものです。しかし、それぞれの国が課税してしまうと国際的な二重課税が発生し、経済活動を税が邪魔することになります。そこで、国際協調が行われ、外国法人や非居住者に課税できるのは恒久的施設(PE)がある場合に限る、「PEなければ課税なし」という国際ルールが定着してきました。
また、グループ間の利益に関する問題です。国際的なグループ取引は、第三者取引とは異なった観点から価格が決定され、その結果、利益が他方の国へ移転することがあります。その対策として、グループ間価格を独立企業間価格(ALP)に引き直して課税する移転価格税制が各国で導入されました。多国籍企業に多額な移転価格課税が行われ、国家間で税金を取り合う「税金戦争」と報道されたことを覚えています。二重課税対策として当局が話し合う「相互協議制度」はありましたが、解決には長期間要したことから、当局に対し事前に確認を求める「事前確認制度(APA)」が導入され、現在幅広く行われています。
このようにグローバルな経済取引に対し、二重課税の防止を中心に長年国際協調に取り組み、いわゆる「全体最適」に近い一定の経済的効果が得られてきました。
しかし、デジタル社会に移行すると、物理的な拠点(PE)がなくてもネット取引が行われます。また、多国籍企業が国際課税のルールや各国の税制のずれを利用して、合法的にどの国でも課税されない「国際的二重非課税」の状況を作出することも問題となりました。
このような問題に対処するため、OECDでは新たな国際協調として2012年より「BEPSプロジェクト」を立ち上げましたが、国際協調の難しさが最近クローズアップされてきました。
(次回に続く)
税理士法人LRパートナーズ
川崎事務所 所長 山下 功起

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします



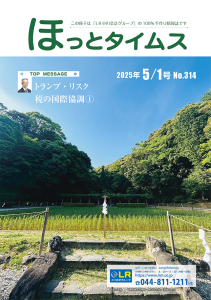
“税の国際協調①” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。