第75回 生成AIと実務の現状③
情報セキュリティ連載
試される人工知能「チャットGPT」の実力
今回は生成AIの技術的な視点ではなく、今後10年、20年後の労働環境の変化にスポットを当て、数字から予測できる未来の現状にどう対応するかについてのお話をさせていただきます。
題材は、『「働き手不足1100万人」の衝撃』 古屋星斗(著)、リクルートワークス研究所(著)という書籍です。
1 本書の内容
2030年現在の働き手「労働人口約7,100万人」が、2040年には「6,000万人」にまで減少するという内容です。1年で100万人の労働人口減少です。他の書籍等でも同様のデータは出ており、パーソル総合研究所でも「2040年までに650万人減少」というデータがあり、年換算で65万〜100万人規模のレベルで労働人口が減少していることが、事実としてあります。
このような話は新聞やマスコミで取り上げられており、耳にされたことがある方はいらっしゃると思います。
2 労働人口減が示す本当の意味
一言で言えば、今まで当たり前のように回収されていたゴミが労働人口減で回収がされない、火事が起きているのに消防車が来ない、というレベルの話になるということです。
3 なぜそうなるのか
労働人口が減れば、全体的な人口も減少すると思われがちですが、総人口は労働人口ほど減りません。
そのため必然的に現状のサービスが維持出来ずに、インフラ等の重要なサービスにも影響がでるというものです。社会保険料の負担額が増えるのと同様の構造です。
本書には、実例としてすでに地方を中心にインフラ維持が厳しくなっている話、例えば建設会社の人員がそろわず、道路などのインフラ工事を断らざるをえない状況が掲載されています。
このように労働人口減少の流れは止められないのが現状です。
この書籍では、労働人口減少への対策をいくつか提案しており、提案の1つにやはり機械化、自動化の話を挙げています。
4 従来の機械化、自動化の書籍との違い
ただ、機械化、自動化の話をしている書籍が多い中で、そこを重要な点にあげているのが、他の書籍とは異なる部分です。現場の流れを熟知している従業員が中心となって、現在の業務に機械化、自動化を導入する動きを起こすことが重要としています。
本書では、自動化の話になるとシステムやエンジニアのような人がいないと進まないと思われがちですが、アプリケーションの進化がはやく、専門的知識がなくても導入しやすい状況になっている点を指摘しています。
本書で書かれている対応策の冒頭にも書かれていますが、どの道労働力不足の煽りを受けてしまうのは避けられないので、組織として自動化、機械化の仕組みの取り組みを始めることを勧めています。
5 自動化、機械化の仕組みはすでに構築されている
ここからは、実際に当社の現場レベルで体感している話です。
自動化というと、ロボティクス・プロセス・オートメーション(RPA)ツールなどを導入しないとできないように思われますが、すでにあるもの同士の組み合わせで手作業は軽減されます。
例えば、売上について販売ソフトやエクセルシートなどパソコンで管理されているケースがあると思います。
上記の例で会計ソフトへデータを入れる場合、恐らく中小企業の多くが、売上データを印刷して会計ソフトに手入力をしていると思います。会計ソフトを含む多くの経理関係のソフトは、データの取込口と取出口を持っています。そもそもの作りとして、データ連携ができる仕組みを相互間で持っています。
さらに、昨年消費税のインボイス制度が開始されましたが、こちらも事業者間で請求書のやり取りをしやすくするため、業者間をつなぐプラットフォーム事業者が、急激に拡大しています。
これらのプラットフォーム事業者や大手事業者の専用サイトからデータを抽出し、経理ソフトへ取り込むことができるようにもなっています。
このように、経理業務の省力化は、自動化ソフトを導入することなく行うことができる環境が、すでに整いつつあります。
この仕組みが理解できれば、給与、クレジットカードや、その他のデータを取り込もうという意識が、組織内に生まれます。
6 自動化の利点
既存にあるもの同士のデータを取り込むことで生じる主な利点は、下記の3つが挙げられます。
• 入力時間がほぼなくなる
• 入力ミスがなくなる
• チェック時間が軽減される
このように現在あるものだけで機械化され、初歩的ではありますが労働人口減少に対応した労働環境が実現します。ここで重要なのは、変われたという認識が現場で生まれることです。
どの道きてしまう労働人口減少です。自動化、機械化等の業務プロセスを変更させるのはすぐにできることではありませんが、まだ時間の余裕はあります。
当社はデータ連携のノウハウを構築してきました。
データ連携のお手伝いをすることが出来ますので、一度ご相談いただければと思います。
《参考文献》
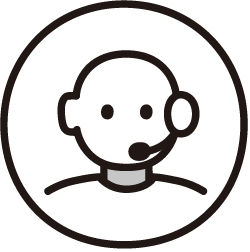 『「働き手不足1100万人」の衝撃 2040年の日本が直面する危機と“希望”』
『「働き手不足1100万人」の衝撃 2040年の日本が直面する危機と“希望”』
古屋星斗(著)、リクルートワークス研究所(著)

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします




“第75回 生成AIと実務の現状③” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。