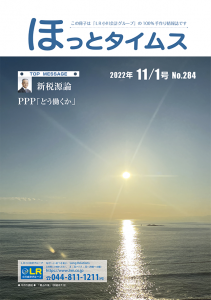成年年齢の引下げによる税制への影響

明治時代から約140年間、日本では成年年齢は20歳と民法で定められていました。
この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。
成年年齢の引下げによる税制関係の影響として主に以下のものが挙げられます。
【贈与税】
⒈贈与税の税率の特例
父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率が適用されます。
その特例制度を受ける受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられます。
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
⒉相続時精算課税
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。
相続時精算課税適用者の年齢が「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上」に引下げられます。
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
⒊住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住用家屋の取得等に充てるための金銭を取得した場合に一定額まで非課税になる制度です。
受贈者の年齢が「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上」に引下げられます。
令和4年4月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
⒋結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
父母や祖父母などの直系尊属が受贈者(20歳以上50歳未満の人に限る)の結婚・子育て資金に充てるために、金融機関に金銭等の信託等(結婚・子育て資金管理契約)をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち、受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用は、300万円を限度)までの金額に相当する価額については贈与税が非課税になる制度です。
結婚・子育て資金管理契約が令和4年4月1日以後の場合、受贈者の適用年齢が「18歳以上50歳未満」となります。
【相続税】
⒈未成年者控除
相続または遺贈により財産を取得した人が未成年者である場合、下記の算式により計算した金額を、相続税額から控除する制度です。
《控除額の算式》
10万円×(※20歳-相続開始時の年齢〈1年未満切捨て〉)
※ 20歳が18歳に引下げられます。
令和4年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産にかかる相続税について適用されます。
成年年齢の引下げにより税制への影響がある規定をご紹介しました。
「住宅取得等資金の非課税」「結婚・子育て資金の非課税」、「相続時精算課税」は対象が拡大し、相続や贈与の検討の余地が広がったものとなりました。
《参考文献・出典》
国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします