生命保険金と死亡退職金の税務上の取り扱い
♡生命保険金と死亡退職金の非課税枠
生命保険金と死亡退職金は、どちらも相続税の計算において非課税枠が設けられています。
非課税額は、一律の金額ではなく、「500万円 × 法定相続人の数」という計算式で算出されます。したがって、法定相続人の数が多ければ多いほど、非課税となる金額が増えます。
生命保険金に関しては、日本の保険業者から受け取るものだけでなく、外国の保険業者から受け取る保険金も相続税の課税対象となるため注意が必要です。
♡相続税対策としての生命保険の活用
生命保険金は、相続財産から一定額を控除できることに加え、相続税の納税資金の調達方法としても活用できるという利点があります。
♡死亡退職金の詳細な取り扱いと注意点
 死亡退職金とは、死亡後にその遺族が受け取る退職金のことを言います。
死亡退職金とは、死亡後にその遺族が受け取る退職金のことを言います。
死亡退職金については、支給のタイミングによって税務上の取り扱いが異なります。
① 被相続人の死亡後3年を経過してから支給が確定した退職金は、相続税の対象とはならず、その遺族の一時所得として所得税と住民税が課税されます。
② 被相続人が生前に退職して受け取った退職金については、退職所得として、退職した本人に所得税と住民税が課税されます。
③ 生前に退職した場合であっても、その退職金の支給金額が被相続人の生前に確定せず、かつ死亡後3年以内に確定した場合は、その退職金は死亡退職金とみなされ、相続税が課税されることになります。
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
生命保険金と死亡退職金は、いずれも法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられており、納税資金の確保に有効な手段となります。これらの制度を理解し、効果的に活用することが大切です。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします


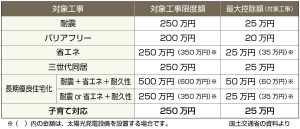

“生命保険金と死亡退職金の税務上の取り扱い” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。