現行の遺言制度とデジタル化について
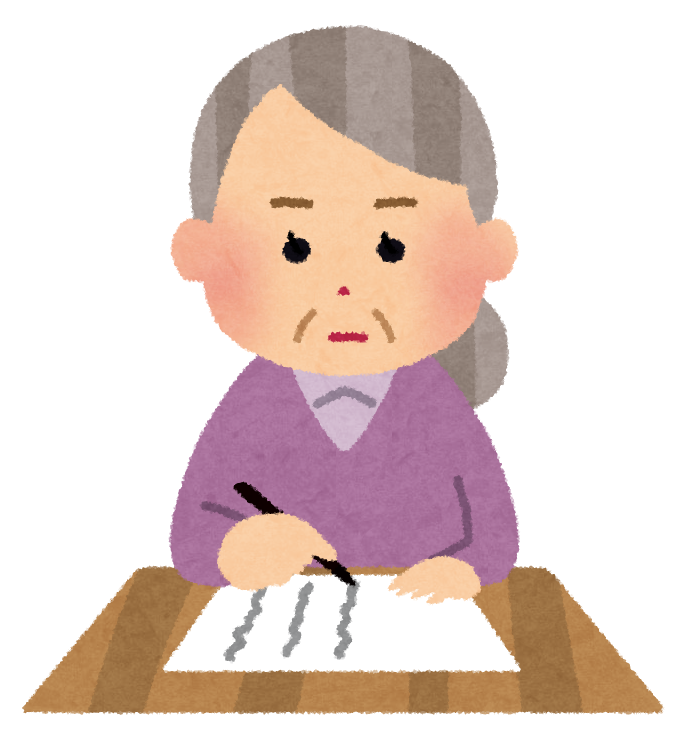 遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
この遺言を自分で作成する場合(自筆証書遺言)、手書きの必要があり、高齢者にとって本文全文を手書きするのはハードルが高いといえます。法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、この作成にあたっての負担軽減を図るためにパソコンで作成することができないかなど見直しに向けた検討が始まっています。
そこで、現行制度における遺言書の種類と、デジタル化に向けての課題をまとめてみました。
【遺言書の種類について】
1 自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付、氏名を自署しこれに押印する方式です。添付する財産目録は手書きである必要はなく、パソコン等で作成することができます。なお、押印については認印でもよいとされています。デメリットは、紛失・改ざんのおそれがある点です。
このデメリットに対応する方法として、令和2年7月から「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
自筆証書遺言書保管制度
この制度は、全国312カ所の法務局で利用することができます。この制度の長所は次のようなものです。
① 適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難のおそれがなく、また、偽造や改ざんのおそれもありません。
② 無効な遺言書になりにくい
民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため外形的なチェックが 受けられます。ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません。
③ 相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定されたかたへ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されます。
④ 検認手続が不要になる
遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要がありますが、この保管制度を利用すれば、検認が不要となります。
2 公正証書遺言
2人以上の証人の立会いにより、遺言者が趣旨を口述し、公証人が遺言書を作成します。
原本は公証人役場で保管します。「公正証書」とは、第三者である公証人が頼まれて作成する公文書になります。公文書のため証明力と執行力があり、法的紛争が起こった際にも信頼性が優れています。
デメリットは、遺言内容の秘密が保持できないことと、公証人の費用がかかることです。
自筆証書遺言、公正証書遺言の他に、利用数は少ないですが、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらう「秘密証書遺言」があります。
【遺言制度のデジタル化にむけて】
遺言のデジタル化の検討は、政府が令和4年に定めた規制改革実施計画などで宣言されました。デジタル化で高齢者の負担を減らし、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便に作成でき、遺言の適切な活用を促す方針です。また、遺言の利用を広げることで、相続トラブルを減らす狙いもあります。
ただ、デジタル化に向けての課題は多くあります。デジタル化した場合、本人が作成したことをどのように証明するのか。他人による変造をどう防ぎ、どう保管するのか。また、パソコンによる作成だけではなく、ビデオによる録音・録画も認めるのか、等々の課題があります。
《参考文献》
政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」
2024年3月17日付産経新聞

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします




“現行の遺言制度とデジタル化について” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。