令和7年新設の育児休業関連新制度
 令和6年6月5日、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が成立し、「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の2つの制度が新設されることとなりました。
令和6年6月5日、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が成立し、「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の2つの制度が新設されることとなりました。
これは、子育てに係る経済的支援の強化、共働き・共育ての推進等を目的としたものです。
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
■「出生後休業支援給付」とは
夫婦そろって育児休業を取得した場合に、従来の育児休業給付に一定額が上乗せされる制度で、育児休業中も一定期間、休業前の手取り額を保証しようというものです。
男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付(現給付率67%)と併せて給付率80%(手取りで10割相当)へ引き上げることとされました。男性の場合は、令和4年10月から施行された「出生時育児休業(産後パパ育休)と併せての活用も想定されます。
なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合等は、配偶者の育児休業の取得を求めずに支給されます。
■「育児時短就業給付」とは
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者が時短勤務をする場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。時短勤務を選択することによる賃金低下を補うことで、時短勤務の利用を促進する狙いがあります。
支給要件は、
① 2歳未満の子供を育てる時短勤務者であること
② 時短勤務の開始日より前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あること
の2点で、対象労働者の労働日数や労働時間には要件はありません。もちろん、男性の被保険者であっても要件を満たせば支給されます。
時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%が賃金の上乗せで支給されますが、時短勤務後の賃金と給付額の合計が時短勤務前の賃金を超える場合は給付率が引き下げられます。
■この2つの制度は
令和7年4月1日に施行されます。
今後、男性の育児休業取得や、時短勤務が益々推進されることも予想されますが、会社としては対象となる方が安心して育児休業や時短勤務ができるよう、組織の体制や業務分担、社内制度などを整えていくことがさらに重要となってくるでしょう。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします



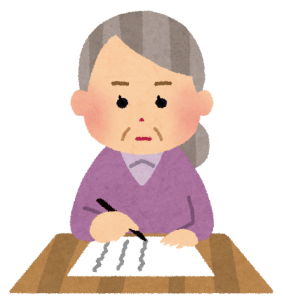
“令和7年新設の育児休業関連新制度” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。