第73回 生成AIと実務の現状
情報セキュリティ連載
試される人工知能「チャットGPT」の実力
2023年12月、大和総研は「生成AIが日本の労働市場に与える影響」というレポートを発表しました。
生成AIの開発で先行する米国市場では、労働市場と生成AIについてのレポートはありますが、日本ではまだほとんどない状況のなか、大和総研は早い段階で発表しました。
それから半年が経ち、社内、社外の実例が出ています。
今回は、レポートの内容について取り上げていきます。
レポートの中で、日本の労働環境において生成AIがこなせる能力から、2つの技術が生まれることが記述されています。
•労働補完技術 •労働置換技術
この2点については、下記の通りに定義付けています。
労働補完技術について
既存の労働者を支援し、生産性を向上させる技術です。
例えば、会計士が従来、紙と鉛筆で行っていた作業をコンピュータで行うことで、業務を効率化し、より多くの顧客対応や、より複雑な分析業務といった付加価値の高い業務に時間を割けるようになるケースが考えられます。
労働置換技術について
従来、人間が行っていた作業を自動化し、労働者に取って代わる技術です。
例えば、リンゴ農園で、従来は人間が行っていた収穫作業を収穫ロボットが代わりに行うようになるケースが考えられます。労働置換技術は、労働者の仕事を奪い、雇用を喪失させる可能性があります。
重要な点は、多くの新しい技術は、労働補完技術と労働置換技術の両方の側面を併せ持つということです。どちらの側面が強く現れるかは、技術の特性、市場の需要、求められるスキル、労働市場の構造など、さまざまな要因によって異なってきます。
例えば、米国の自動車産業では、20世紀前半に電気や内燃機関の実用化といった技術革新が起こりました。この技術革新は、一部の熟練工の仕事を奪いましたが、同時に、より多くの作業員や、トラック運転手やガソリンスタンド店員といった新たな職業を生み出しました。結果として、米国では自動車という新技術は、労働補完的な側面が強く、雇用増加に貢献しました。
一方で、同時期の英国の産業革命では、蒸気機関の導入により、高賃金の熟練工の仕事が機械に置き換えられました。 このケースでは労働置換的な側面が強く、熟練工の失業や貧困層の拡大といった社会問題を引き起こしました。
生成AIは、ホワイトカラーの仕事を中心に、多くのタスクを自動化する可能性を秘めています。生成AIが労働補完技術として機能するか、労働置換技術として機能するかは、今後の技術開発や社会状況によって大きく変化する可能性があります。
★ 生成AIの普及が先行する米国での事例
本レポートで、米国の雇用について生成AIの影響を受ける可能性が高い職業は、会計士、数学者、税理士、ライター・作家、翻訳者、ウェブデザイナー、ジャーナリストと分析されています。その理由として、下記の3つの前提条件を満たしているとしています。
❶ 政治的に受け入れられる
❷ 自動化可能なタスクが存在する
❸ 労働コストに比べて十分に安い
この前提条件を日本の現状で検証してみます。
❶ 政治的に受け入れられる
まず、政治的に受け入れられているということについてですが、岸田政権は2023年日本の広島で開かれたG7で生成AIの規制のあり方を協議する「広島AIプロセス」を主導しています。また、岸田首相を本部長とする「新しい資本主義会議」でも、産業界での利活用に向けた環境整備を進めています。
❷ 自動化可能なタスクが存在する
これは日本に限ったことではないですが、上記でリストアップされているホワイトカラーの職業には、自動可能なタスクが存在しています。
ここでいう自動可能なタスクとは、書面から文字を読み取り、その文字データからどうするかの判断をするといった、ホワイトカラーの職種なら必ずあるタスクを指します。
❸ 労働コストに比べて十分に安い
価格についてですが、大体企業利用のアカウントで1人あたり3,000〜4,000円程度で利用できる状況です。
当社が使用しているGoogleのVertexAIは定額制ではないですが、1処理に0.03円程度で処理ができ、コストは非常に安価で処理ができている状況です。
上記3点は日本においても米国同様条件を満たしており、日本の労働社会にも浸透する条件を満たしていると思います。
次回、これらを踏まえ、現時点の生成AIが労働補完技術、労働置換技術、どちらの立ち位置にあるかについて考察します。
《参考文献》
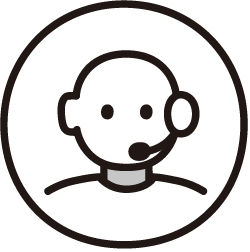 大和総研2023年12月8日「生成AIが日本の労働市場に与える影響①」
大和総研2023年12月8日「生成AIが日本の労働市場に与える影響①」

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします


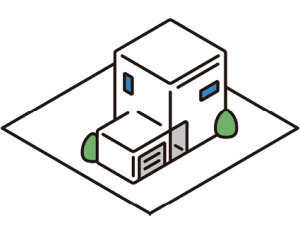

“第73回 生成AIと実務の現状” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。