「遺言」について

遺言には、遺産相続をめぐる財産争いを防ぐ効果があり、それを防ぐため、遺言書を活用する人が増えています。
内容や形式が自由で被相続人の思いを記載する〝遺書〟とは異なり、〝遺言書〟には財産を贈与する法律上の効果があります。夫婦に子供がいない場合や子供の配偶者に相続させたい場合、一代飛ばして孫に相続させたい場合などでも遺言書を活用することができます。
遺言書には、
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
の3種類があります。
1 自筆証書遺言
定められた方式で作成し、遺言者本人が署名押印します。
証人がいらず、遺言を書いたことや遺言内容を秘密にしておくことができ、費用もかかりませんが、遺言書が発見されない場合や発見されても隠蔽・破棄されるおそれがあります。また、開封するには裁判所の検認が必要です。
※各頁に署名押印すれば、財産目録については自書でなくパソコン等で作成したものでもよくなりました。(平成31年1月13日以降)
※申請をすれば法務局で保管してもらうことが可能です。保管期間は、死亡日から50年間で手数料はかかりますが、裁判所の検認は不要となります。(令和2年7月10日以降)
2 公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。2人の証人と手数料はかかりますが、隠蔽や破棄される危険性はなく確実な遺言書です。裁判所の検認も不要です。
3 秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を封印します。遺言書を封印したまま公証人と証人2人の前に封書を提出し、自分の遺言書であることを申し述べます。
遺言内容を秘密にしておくことはできますが、手数料がかかり、開封するには裁判所の検認が必要です。
トラブルを避けるためには、手数料はかかりますが、事前に専門家のチェックも受けられる、2公正証書遺言がすぐれているでしょう。遺言書は書き直すことも可能です。その場合、日付の新しいものが有効となります。まずは、自分の思いを紙に書いてみてはいかがでしょうか。実際に紙に書いてみることで、自分の新たな思いに気づいたり、気持ちの整理につながったりするかもしれません。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


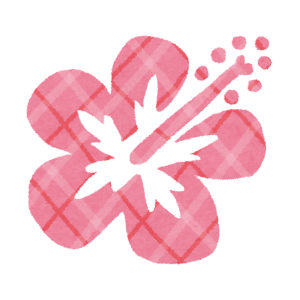

“「遺言」について” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。